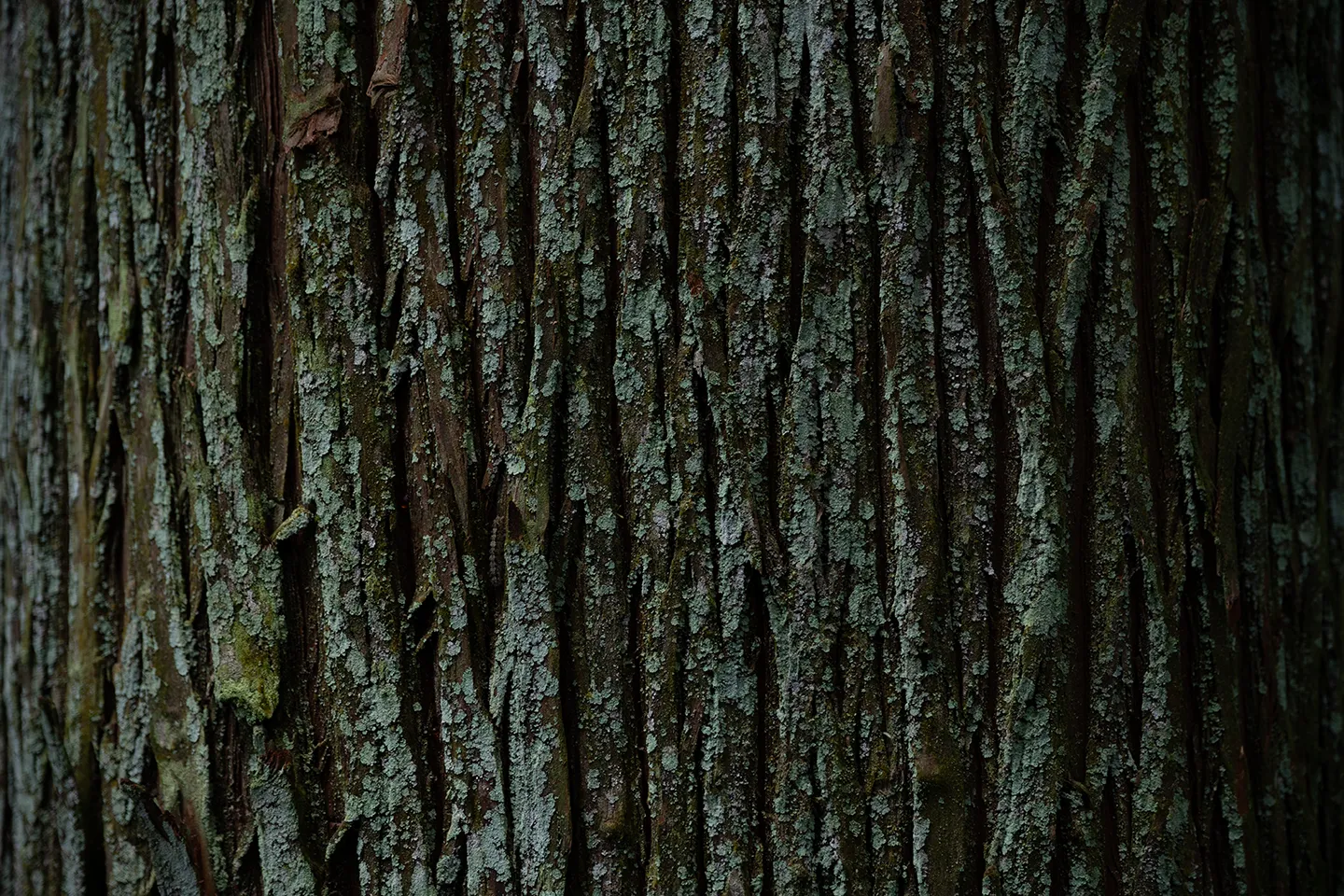気候変動の影響が日常に迫る今、私たちはどのように脱炭素社会を実現していけるのでしょうか。今回は、気候変動の国際的な専門家である九州大学の馬奈木俊介教授に、古材の再活用を通じて環境負荷の低減と新たな価値創造を目指す、私たちの「KATARITSUGI」プロジェクトについてご意見をいただきながら、脱炭素社会の実現に向けたヒントを探りました。
━━━本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございます。近年、山火事や大雨、気温の上昇など気候変動の影響を肌で感じる機会が増え、脱炭素社会が大事だと感じています。古材は脱炭素社会において、どのような貢献ができるのかお考えをお聞かせいただけますか。
馬奈木教授:古材は、日本特有の資源です。通常なら廃棄していくものを再活用していくことで、新たな資源の消費を抑えることができます。これは環境負荷の低減に直結する大きなメリットです。
質の面でも古材は有効活用するべきだといえます。
古材として残っているものは、長い年月で試練を乗り越えてきた強靭な素材だからです。
というのは、以前の話になりますが現代の工業製品、例えばコンクリートでいうと古いコンクリートよりも新しく開発されたコンクリートのほうが壊れやすい、という事例がありました。
どうしてそういったことが起こるのかというと、長期間を経た検証ができなかったからですね。
以上から、環境効果へのプラス、高品質な住宅の材料として、古材は活用するべき資源ですね。
私はIPCC(気候変動政府間パネル)でも活動をしていますが、特にここ5年の気候変動のスピードはIPCCの予測をはるかに超えています。
古材を新しい住宅へ再活用することは、住む方はもちろん、その家を訪れた人に古材という選択肢があることを知る良いきっかけにもなると考えています。

━━━地球温暖化の進行は深刻な状況なのですね。そのような中で、古材を活用した住環境は、住む人、特にお子さんへの住教育にも良い影響を与える可能性があると考えています。
馬奈木教授:緑の環境価値(みどりのものさし)という研究 があります。人々の環境への意識の高さを研究しているものですが、そこで分かっていることは、子供の頃に森や自然などに触れたことがあると、大人になってからそうした環境への価値認識が高いということです。
だから古材を使った家で育ったり、遊びに来た友達が古材に触れたりできることは、わざわざ遠くまで行かなくても、身近な場所で自然を感じられる良いきっかけになります。
━━━人々の暮らしの中で脱炭素社会を当たり前にしていくために、日本ではどのような課題があるとお考えでしょうか。
馬奈木教授:脱炭素を自分ごととして捉えることが、最も重要な課題でしょう。
企業は、画期的な技術開発に目を向けがちでCO2を半分にしようと頑張るのですが、2050年までに半減すればいいのであって、今1割減らすだけでも十分な進歩です。
4割だと足りない、というのは目標が高すぎますね。
また、水素や原子力も取り出されますが、スケールが大きすぎて個々の企業や個々人では何をやっていいのか想像できないテーマです。
ある時高校の先生に、脱炭素社会を実現するために日常的には何をすればいいのですか?と聞かれました。
子供たちに「電気を消しましょう」とか「ゴミ拾いをしましょう」と教えればいいのでしょうかと聞かれたのですが、それよりも勉強することのほうが大切です。
学んで、自分が楽しくて環境にも良いことができるほうが大事で、持続可能じゃないですか。
例えば、今、筋トレが流行っています。たいていの人はモテたくて筋トレを始めます。
そのうち、いろいろと調べていくと、筋肉をつけること自体が楽しくなっていって、鏡に映る自分が美しいと感じるんですね。
自分にとって楽しくなった人は続けるし、きつくなった人はやめてしまいます。
CO2削減効果が小さくてもいいから、自分ができる範囲で楽しんでできることをやっていけばいいんです。「こんなことやっても意味がないのでは?」と考えずにできることから始めていってほしいです。
考えすぎで動けない人や組織が多い中で、小田急不動産さんが数年をかけて「KATARITSUGI」プロジェクトをスタートさせたことは素晴らしいことだと感じています。
今回の古材を使った住まいも、住みやすさを実感できて環境に良いことを見つけていくプロセスが大事なんです。
「KATARITSUGI」プロジェクトが全国に広がるきっかけになってほしいですね。

━━━現在、教授が手掛けられているプロジェクトについてお伺いしてもよろしいでしょうか。
馬奈木教授:私は、国連の環境計画(UNEP)のプロジェクトで、10年前から代表を務めています。政府や研究者、その他多種多様な人たちとの合意形成のために話し合いを行うのですが、価値観の変化は時間がかかるものです。
その活動の中で、その国にはその国の成功事例が必要で、日本には日本国内の成功事例が必要ということに気づきました。
そこで、福岡県の久山町をはじめとする複数の自治体と連携協定を結び、行政、議会、市長の了承を得て活動を行っています。
具体的な事例があることで、他の自治体や企業も関心を持つようになってきています。
現在は「NCCC(自然資本クレジットコンソーシアム)」という組織を立ち上げ、自然資本をクレジットとして普及させる仕組みづくりにも取り組んでいます。
これは、単なるCO2削減だけでなく、社会課題を解決することを目指すものです。
産学官で日本独自の成功事例を作り、それを世界に発信していこうと取り組んでいます。
「KATARITSUGI」プロジェクトは古材を使用した住宅の需要を小田急不動産さんが見出して始めたもので、将来の新しい価値を生み出す源泉です。こうした動きを広げていく仕組みは私も興味がありますね。

━━━ありがとうございます。話が変わりまして、海外の状況についてもお伺いしたいのですが、脱炭素に向けた取り組みは、日本と比べて進んでいるのでしょうか。
馬奈木教授:例えば、オランダは自転車利用が非常に盛んですが、それは健康意識の高さと、海が多く海抜が低い堤防の国であるという背景から、気候変動に対する危機意識が根付いているからです。
ただし、一般市民の意識が高いとは限りません。
行政が、時には強力に政策を推進して実現しています。
日本は日本で水害のリスクが高い。夏は暑く、冬は寒い。そういった島国の特徴を踏まえ、効果的な対策を推進していくべきです。
海外の良い事例も参考にしながら、ヒントを得ていければいいですね。

━━━小田急不動産という不動産会社が今後どのような発信をするべきなのか、アドバイスをいただけますか。
馬奈木教授:発信すること自体がまず大事で、発信が価値になっていくと思います。
発信が他の企業や人々に考えるきっかけを与えることになりますし、古材×不動産・鉄道の取り組みで調べたときに「KATARITSUGI」がヒットすると嬉しいですよね。
小田急不動産さんの今回の取り組みがほかの地域の鉄道・不動産会社へ波及し、次に改善された成功事例が生み出されて、それがさらに発信されていく、という流れが理想ですね。
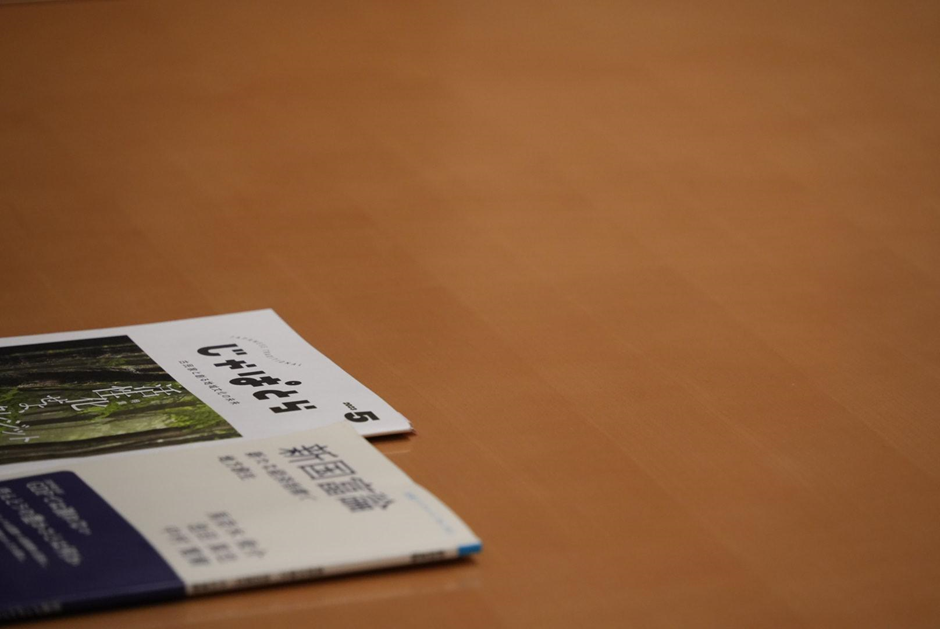
━━━「KATARITSUGI」プロジェクトは、クレジット化、つまり脱炭素の取り組みの効果の数値化・認証する制度に該当しますか。
馬奈木教授:カーボンクレジット化するためにはいろいろな条件がありますが、どのように認証されるかを設定・検証すればクレジット化に該当することができます。
クレジット化の評価によって、より意義や価値のあるプロジェクトになっていくと感じます。

━━━ありがとうございます。最後に、弊社の「KATARITSUGI」プロジェクトに興味を持っている方々に向けて、メッセージをいただけますでしょうか。
馬奈木教授:興味を持って環境について調べていただきたいですね。例えば木1本でどのくらいのCO2が吸収されるのだろう、電力に比較するといくらになるのだろう・・
そのような自分の生活や身近なところでイメージできるよう比較しながら勉強していただくといいと思います。
自分が興味を持てる分野であれば古材でも、自然でも、地域のことでもなんでもいいです。
知識が身について新しい発見や気づきを得て、そこから脱炭素につながる小さな行動に繋がると嬉しいですね。

━━━確かに、知ることから全てが始まりますね。馬奈木教授、本日は大変貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。
馬奈木教授:こちらこそ、ありがとうございました。小田急不動産様の今後の取り組みを応援しています。
お話しを伺った方:
馬奈木 俊介
九州大学 主幹教授・株式会社aiESG 代表取締役・一般社団法人ナチュラルキャピタルコンソーシアム理事長
国連Inclusive Wealth Report Director。気候変動に関する政府間パネル (IPCC) 代表執筆者。OECD貿易と環境に関する共同作業部会副議長等多くの国際機関や企業との連携を実施。日本学術会議サステナブル投資小委員会委員長。著書25冊、学術誌論文500本。日本学術振興会賞受賞他多くの受賞歴を有する。

インタビュアー:
小田急不動産株式会社 KATARITSUGIプロジェクトメンバー