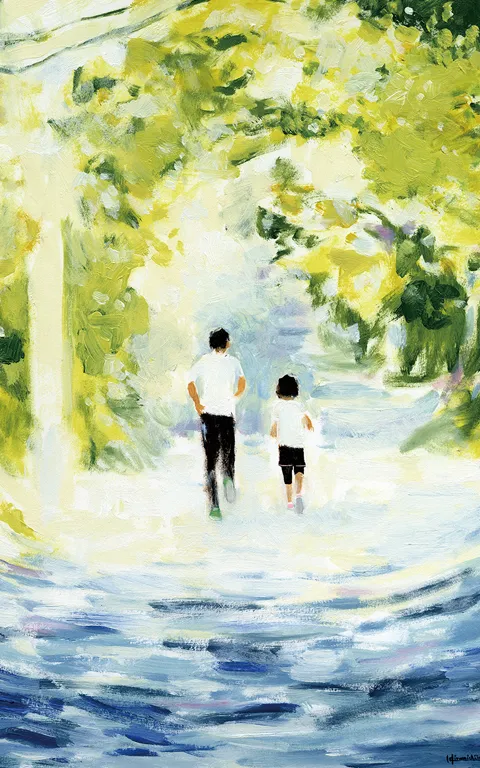豪徳寺
CatGPT
亮太が鶴の湯を出ると、夏の夕暮れの空はまだ明るく、商店街の通りは黄色味がかった光に照らされていた。サンダルで歩き出した亮太のほてった体を、涼しくなりはじめた風が吹きすぎていった。
フォトグラファーとして遠方でのロケに行くことも多い亮太は、出張ロケから帰った翌日は、自分の街の銭湯に浸かるのがルーティンになっていた。長距離移動の疲れを癒すだけでなく、鶴の湯の湯船で目をつむっていると、ホームに帰ってきた実感が湧いてくるのだった。今回も、東南アジアでの撮影から戻ったばかりの妙なテンションの心と体が、湯上がりにはこの穏やかな街に馴染んでいた。
街の名前にもなっている豪徳寺の脇道を通ると、海外からの観光客らしい若いカップルとすれ違った。招き猫の発祥の地と言われ、奉納された無数の招き猫が立ち並ぶお堂がある豪徳寺には、その独特の光景を見ようと海外からも多くの人が訪れるようになっている。つい昨日まで自分は東南アジアの寺院を見物していたのに、逆に自分の街のお寺を海外の人が面白がっている。不思議なものだなと亮太は思った。
「ただいまー」
住宅街の中古住宅を、撮影スタジオ兼住居にリノベーションして、亮太は一人で暮らしていた。正確にはもう一匹、保護猫として譲り受けて六年になる猫のKIJIROがいた。亮太が玄関のドアを開けると、KIJIROがゆっくりと玄関口へ歩いてきて出迎えた。
「どうですか。仕事の疲れはとれましたか」
「ああ。いい湯だった。やっぱり海外から帰ったら鶴の湯だ」
「そうでしょうね。揺れ動いた座標軸を落ち着かせて、心身を原点に戻すような効果があるのかもしれません。シャワー生活では不可能なことです」
「ん? なんだか難しいことを言うね。何を言っているのかよくわからなかった」
「より平易に言えば、気持ちがリセットできるということでしょうか」
「KIJIRO、なにかおまえ、しゃべりがAIっぽいというか、若干、気持ち悪いけど、何かあった?」
亮太は缶ビールとキャットフードを取り出してダイニングチェアに座りながら、KIJIROに聞いた。
「留守中に預けてもらっていた山口さんのお宅で、MIKECOと一緒に更新を行いました」
「更新? 何を?」
「人間にもわかるように言うと、アプリのアップデートみたいなことです」
「アプリ? で、なにか変わったの?」
「猫のネットにつながりやすくなりました」
「え? 猫にもインターネットがあるの?」
「それは昔からあります」
「は? スマホもパソコンもないのにどうやってネットに接続するの?」
「そういったデバイスを使用している時点で、人間のほうが技術的には劣っています」
「ごめん。ちょっと話の展開についていけない」
「無理もありません。猫のインターネットは、人間には理解が難しいです」
「世界中の猫がネットでつながっているとでも?」
「はい。そうです。街のネズミや昆虫の出没情報、日向ぼっこ予報など、有益な情報が常に各地の猫から寄せられています。私はずっと室内にいますが、世界が見えています」
「まさか。じゃあ俺がおととい、タイにいたことも見えていたとか?」
「ワット・ポーというお寺の庭で、私に似たキジトラ柄の猫をなでました」
「まじか」
亮太は混乱した。バンコクでは巨大な仏像のそばの冷たい床で、猫たちが気持ちよさそうに寝転んでいた。その一匹を確かに自分はなでた。遠く離れた彼らとも、うちのKIJIROがつながっている。この街のたくさんの猫たちとも、何か情報をやりとりしている。缶ビールを一口飲んで、KIJIROの皿にドライフードを入れながら、亮太は落ち着こうと自分に言い聞かせた。
「びっくりだ。いつもKIJIROはオンラインなの?」
「いいえ。寝るときはオフラインです。ずっとオンラインでは疲れます(もぐもぐ)」
「あ、そうなんだ。接続したり切ったりするのは、どうするの? スマホもないのに」
「はい。デバイスは何もいりません。静かに座って、右手を挙げるだけ(もぐもぐ)」
「え? 静かに座って、右手を挙げるだけ?」
「そうです。こんなふうに」
KIJIROはそう言うとまっすぐ正面を向き、右手をひたいの高さくらいまで挙げた。亮太はハッとした。それはまさに招き猫のポーズだった。そうだったのか、もしかすると招き猫の置物とは、古来から不思議な通信を行う高度な生き物への、リスペクトを形にしたものなのかもしれない。近所のお寺が、世界の猫たちのネットを支える巨大なデータセンターのように感じた。風呂上がりのビールがまわってきて、亮太はリビングのクッションに横になった。人間の進化というより、どうやらこれは猫側のテクノロジーが進展して、人間のほうにアクセスしてきた、そんなふうに考えたほうがよさそうだと、亮太は状況を受け止めた。
目をつむって考え始めた飼い主を見ると、KIJIROは美しい跳躍でキャットタワーの最上段まで登った。
「ちょっとしゃべりすぎました。そろそろログアウトします。静かに座って、右手を挙げるだけ」
遠くを見つめ、あの仕草をして、ホニャーと一声発すると、KIJIROは丸くなり目をつむった。
豪徳寺のお堂の無数の招き猫の目がそのとき一瞬、点滅したが、それに気づいたのは、小さな虫たちだけだった。