不動産売却のノウハウ

相続した実家を売却する流れや
税金について詳しく解説
実家を相続すると、資産が増えると思われがちです。
しかし、人によっては住宅ローンや修繕費などの負債を抱えたり、定期的な支払いが発生するケースも珍しくありません。
実家を売却する場合、相続の手続きだけでなく不動産会社の査定やかかる税金などについて理解する必要があります。
相続した実家を売る手順と注意点、発生する税金について解説します。
不動産売却 費用・税金2024年12月11日
目次
実家の相続から売却までの流れ
ここでは、実家を相続してから売却するまでの流れについて解説します。
実家を売却するかを決める
まずは、実家を売却するかどうかを決めます。
実家を売却するメリット
実家を売却するメリットは次の2点です。
- 財産を平等に分配できる
- 維持費がかからない
実家を売却することで相続人間でのトラブルを未然に防げます。不動産と違い現金は平等に分割できるためです。
また、不動産は所有しているだけで固定資産税が発生するため、売却することで支払いを避けられます。
賃貸が難しい住宅の場合、行政から「特定空き家」に指定され罰金の支払いが発生する可能性もあります。売却することでそのようなリスクを避けられます。
実家の売却を後悔するケースと対策
以下は実家の売却を後悔するケースです。
- 思い出の場所をお金に替えてしまう罪悪感
- 相場より低い価格で売ってしまう
実家は、家族との思い出の場所。それを売却するのですから、誰もが罪悪感を抱くのではないでしょうか。
対策としては、気持ちを整理する必要があります。家族との思い出を振り返り、次へ進む心の準備をしましょう。
空き家になった実家を売る場合は、相場以下の売却価格になる可能性があります。
空き家を放置すると建物の劣化が進み価値が下がるため、売却額が下がる傾向が強いです。
リスクを恐れて焦って売却することになり、相場より安売りしてしまうかもしれません。
実家を売却する際は複数の不動産会社に価格査定を依頼しましょう。さまざまな査定額からおおよその相場価格を把握できます。合わせて自分でも相場を調べておきましょう。相場を調べるには、物件検索サイトで売り出し価格をチェックするなどの方法があります。
名義変更
売却が決まったら、次は法務局で名義変更を行います。名義変更しないと相続した実家を売ることができません。なお、2024年4月からは、相続の発生を知った日から3年以内に相続登記することが義務付けられました。
価格査定
続いて売却相場を把握するために、実家の査定を受けます。プロの視点から根拠のある査定を行うことが重要です。
不動産会社には次の2つの査定方法があります。
- 簡易査定(机上査定)
- 訪問査定
簡易査定
不動産会社がレインズ(不動産流通標準情報システム)のデータベースを活用し、周辺の成約事例をもとに、おおよその査定額を出します。手軽に査定額を出せますが、物件の詳細な状態は考慮されません。
※レインズとは、全国の不動産情報を一元化したシステムで、物件情報を共有し売買をスムーズに進めるために利用されます。国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営しており、不動産会社しか閲覧できません。
訪問査定
営業担当者が物件を訪れ、物件の内観・外観を確認の上、周辺環境や建物の状態などを総合的に評価して査定額を出します。
媒介契約と売却活動
次に売却を依頼するために、不動産会社と契約をします。
この契約を媒介契約と言います。
| 媒介契約の種類 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
|---|---|---|
| 売主側の決まり | 依頼できる仲介会社は1社のみ | 複数の 仲介会社に依頼できる |
| 不動産会社の義務 | ・ レインズへの物件情報の登録義務あり ・ 売却活動の状況を売主に報告する義務がある |
・ レインズへの物件情報の登録義務なし ・ 売主への報告義務なし |
他にも専属専任媒介契約もありますが、主に上記2つを押さえておけば問題ありません。
媒介契約後、不動産会社は、売却活動に入ります。不動産ポータルサイトへの掲載や自社のホームページへの掲載、レインズへの登録を行い他の業者と情報を共有します。
売主も、内覧対応が必要なため、任せきりにはできません。
売買契約と引き渡し
買主が見つかり、売却価格や条件に合意が取れたら売買契約を締結します。契約時には引渡しの時期、重要事項について確認します。
契約の締結後、買主が売買契約で決められた日に売買代金の決済を行います。同時に、買主に物件の鍵を引き渡し、物件の引渡しが完了します。
また、物件の引渡しと同日に、司法書士の立会いのもとで所有権移転登記が行われます。
実家を高く早く売るには不動産会社選びが重要
実家をできるだけ高く、早く売るには不動産会社選びが重要です。
不動産会社選びのポイントは次の通りです。
- 売買を得意としているか
- 地元の不動産会社
売買を得意としているか
不動産会社には売買仲介、賃貸仲介、賃貸・建物管理など、それぞれの得意分野があります。売買仲介が得意であれば、通常はホームページの会社案内で謳っているので、売却相談をする前に確認しておきましょう。また、直接販売実績を聞くようにしましょう。
地元の不動産会社
地元の不動産会社は、地場の強みを活かした独自の情報を持っています。地域で物件を探している顧客とのつながりも強いため、物件が出たらすぐに連絡できます。
周辺エリアに支店がある大手不動産会社にも同時に依頼しておくと、より高く売れる可能性が高まります。大手には、広告宣伝力や販売力に期待ができます。
相続した実家で損しないための注意点
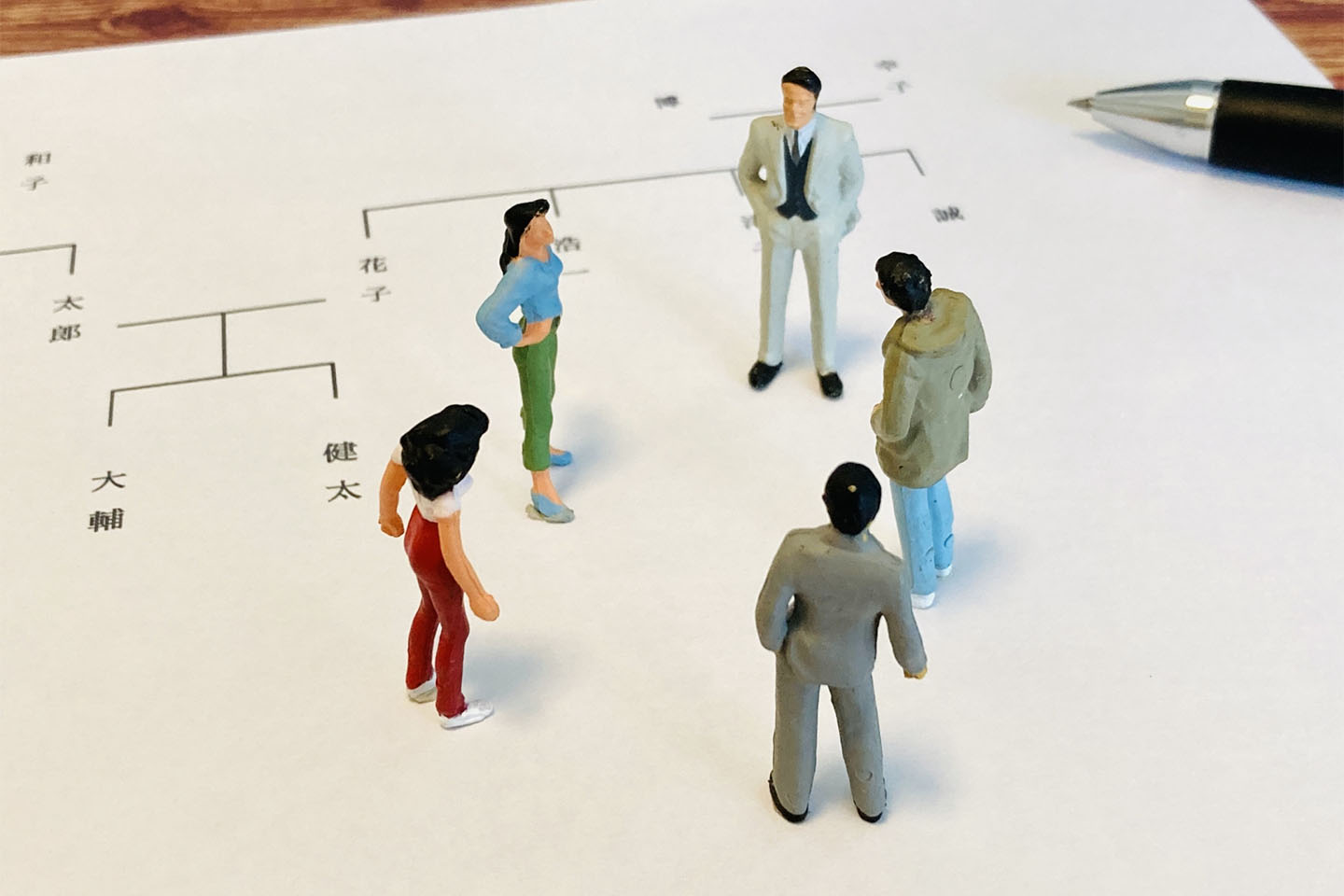
ここでは、実家を相続する際、損しないための注意点をお伝えします。
実家相続の手続きの流れ
まず、大まかな相続の流れは次の通りです。
| 1 | 相続人の確認 | 誰が相続人になるかを調べます。 |
|---|---|---|
| 財産の確認 | 故人がどのような財産を持っていたかを調査・確認します。 | |
| 遺言書の確認 | 遺言書があるかどうかを確認し、その内容をチェックします。 | |
| 2 | 相続放棄 | 必要に応じて、相続を放棄する手続きをします。 |
| 3 | 準確定申告 | 故人の生前の収入に関する最後の確定申告を行います。 |
| 4 | 遺産分割協議 | 遺産をどのように分けるか、相続人同士で話し合います。 |
| 5 | 相続登記 | 不動産の名義を相続人に変更する手続きをします。 |
| 6 | 相続税の申告と納付 | 相続税がかかる場合、税務署に申告し納税します。 |
実家をどうするかは3ヵ月以内に決める
相続が開始したことを知ってから3カ月経過すると、単純承認となり、実家などのすべての財産や負債を相続することが確定します。この場合、借金などの負債があっても相続放棄は原則としてできなくなります。
そのため、財産と負債を調査し、多額のローンが残っており負債の方が多い場合などは、3カ月以内に相続放棄を行うのが賢明です。
相続した実家をすぐに売った方がいいケース
次のような場合は、実家をすぐに売った方が良いでしょう。
- 相続税の支払い資金がない場合
- 相続人間で公平に分けたい場合
- 相続税の取得費加算の特例を利用できる場合
- 相続した空き家特例を使う場合
相続財産の不動産の割合が多く現金が少ないと、相続税の支払いが難しくなります。
相続人間で公平に分けたい場合は、売却して得たお金を分ける「換価分割」が有効です。
相続税を払った後に実家を売却する場合、相続から3年10カ月以内に売却すると、取得費加算の特例により売却益の課税が軽減されます。
空き家特例は一定の条件を満たせば、売却益から最大3000万円の控除が受けられますが、相続から3年以内の12月31日までに売却する必要があります。
遺言書の指示がない場合は、法定相続人全員の同意が必要
遺言書がない場合、遺産相続には法定相続人全員の同意が必要です。兄弟姉妹で実家を相続する場合、財産の分け方について全員で話し合い、合意を得る必要があります。
不動産は現金と異なり分割が難しいため、次のような分け方があります。
- 代償分割:相続人の1人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法
- 換価分割:不動産を売却して得た現金を相続人で分ける方法
- 実家を残すことを優先:不平等になることに全員が合意した上で、1人が実家を相続し、他の兄弟姉妹は他の財産を相続する方法
遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要です。1人でも同意しない場合、協議は成立しないため、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
2027年12月31日までに売りたい
相続した実家を売却する際、「空き家特例」を利用すれば、売却益から最大3000万円が控除され、最大600万円の税金を抑えることができます。この特例は以下の条件を満たす必要があります。
- 昭和56年5月31日以前に建てられた住宅であること
- 取り壊しまたは耐震リフォームを行う前提であること(令和6年以降は購入者によるリフォームも対象)
- 相続が発生してから3年を経過した年の12月31日までに売却すること
- 家屋と敷地をセットで相続し、空き家の状態を保つ必要があること
売却期限は2027年12月31日までです。相続人が複数いる場合は、売却時期によって控除額が変わるので注意が必要です。
査定前に家具などの片付けが重要
査定前に家具などの片付けが重要です。
家具や不要な物が残っていると部屋の広さや状態が分かりにくくなり、物件の印象が悪くなります。
また、不動産会社が処分しますが査定の時点で処分費用を見積もり、その分をマイナス評価にされます。
片付けを行うことで、部屋の本来の広さや状態が明確になり、より正確な査定が可能になります。
時間がない場合は、不動産会社による買取と言う手段もあります。
買取とは不動産会社が直接買い取ることで、買主向けの販売活動や片付けが不要です。
買取を依頼する不動産会社選びのポイント
地元の不動産会社であり、売買を専門としているかを確認しましょう。戸建ての買取の実績がある不動産会社かどうかも重要です。
相続した実家を売却する際の税金と特例
印紙税
印紙税は、不動産売買契約書を作成する際にかかる税金で、契約金額に応じて税額が決まります。納税方法は、郵便局などで購入した印紙を契約書に貼り、消印することで完了します。
■不動産の譲渡に関する印紙税額
| 契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 50万円以下のもの | 200円 |
| 50万円を超え 100万円以下のもの | 500円 |
| 100万円を超え 500万円以下 | 1千円 |
| 500万円を超え 1千万円以下 | 5千円 |
| 1千万円を超え 5千万円以下 | 1万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下 | 3万円 |
| 1億円を超え 5億円以下 | 6万円 |
| 5億円を超え 10億円以下 | 16万円 |
| 10億円を超え 50億円以下 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 48万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
(印紙税額表)
登録免許税
登録免許税とは、所有権移転登記の際に発生する税金です。
相続した実家を売却する際は、相続するとき、売却するときと2回発生することになります。
相続するときの登録免許税
1回目の登録免許税は、相続が発生した際に、被相続人(親)の名義から相続人(自分)の名義に所有権を移転するときです。税率は、不動産の価額の0.4%です。
売却するときの登録免許税
2回目の登録免許税は、相続した不動産を売却する際、買主を新たな所有者として登記するときです。この登録免許税は買主が負担するのが一般的で、税率は、不動産の価額の1.5%です。
(参考:国税庁 登録免許税の税額表)
譲渡所得税(住民税)
譲渡所得税とは 売却した利益に対して発生する税金です。
譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除
(国税庁 譲渡所得 土地や建物を譲渡したとき)
上記の譲渡所得に対して、税が発生します。
譲渡所得税率
譲渡所得税は、不動産の所有期間によって税率が異なります。
| 所有期間 | 税率 |
|---|---|
| 短期譲渡所得(5年以下の所有) | 39.63% |
| 長期譲渡所得(5年超の所有) | 20.315% |
所有期間は、被相続人(親)の取得日から計算される点がポイントです。
取得費
取得費に含まれるものは次の通りです。
| 購入代金 | 土地や建物の購入時に支払った金額 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産業者に支払った仲介手数料 |
| 登録免許税や不動産取得税 | 不動産を取得する際に支払った税金 |
| 登記費用 | 所有権移転登記などの手続きにかかる費用 |
| 設備費・改良費 | 取得後に支出した、資産価値を増加させるための費用(例:リフォーム費用や新たな設備の導入費用)。 |
| 減価償却費相当額 | 建物の取得費には減価償却費が適用されるため、その額を取得費から差し引いたものが適用されます。 |
参考:国税庁 取得費となるもの
相続税
相続税は、被相続人の財産を相続した場合に発生する税金で、現金や不動産、株などのあらゆる資産に対して課されます。納付期限は、相続開始から10カ月以内に行う必要があり、申告が遅れると、加算税や延滞税が課されます。


