不動産売却のノウハウ

不動産売却で税金がかからないケースは?
注意点と節税ポイントも解説
不動産売却時にはどのような税金がかかるのでしょうか。
一般的ですが、実は場合によっては不動産売却で税金がかからないケースもあります。その可能性がある方は条件を正しく把握することで、税負担を大幅に軽減できるチャンスです。
不動産売却で税金がかからない条件、注意すべきポイント、さらに節税対策について詳しく解説します。
不動産売却 費用・税金2025年4月18日
目次
不動産売却で税金がかからないケース
不動産売却では、取引の金額が大きくなりがちです。売却にかかる税金も多額になるので無視できません。そこで、まずは不動産を売却しても税金がかからない4つのケースについて解説します。
売却しても利益が出ない
不動産を売却しても利益が出ない場合は、譲渡所得税はかかりません。不動産売却では、売却したときに譲渡所得に対してかかる所得税・復興特別所得税・住民税をまとめて「譲渡所得税」といいます。譲渡所得金額は、次の式で計算します。
課税譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額(一定の場合)
不動産の売却価額が取得価額を下回るときは、課税譲渡所得金額がマイナスになるため税金は発生しません。なお、譲渡費用には、仲介手数料や測量費、立退料、建物を取り壊して売却した場合は取り壊し費用などが含まれます。
参考:国税庁「土地や建物を売ったとき」
譲渡所得が3,000万円以下
売却する不動産が居住用財産(マイホーム)の場合は、所有している期間に関わらず、譲渡所得から3,000万円まで特別に控除できます。そのため、居住用財産の譲渡所得が3,000万円以下の場合、譲渡所得税はかかりません。
基本的には、現在自身が住んでいる家屋や以前住んでいた家屋を、決められた期限内に売却するときに適用できます。
家屋を取り壊してから売却しても特別控除を受けられますが、「取り壊してから譲渡するまでの間に敷地を貸し駐車場などとして使用していないこと」などの制限があります。
また、仮住まいなど一時的な目的で入居した家屋や、別荘など趣味・娯楽のために所有する家屋も特別控除を受けられません。
また、所有期間が10年以上の居住用財産を売却したときは、「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」と併用が可能です。譲渡所得が3,000万円を超えている場合、3,000万円の特別控除後の譲渡所得金額のうち、6,000万円以下の部分に対しては税率が軽減される制度です。
通常、5年以上所有した不動産を売却するときは、約15%の税金がかかりますが、本特例を適用すると約10%に軽減されます。
参考:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
相続した不動産の売却
自身が住んでいた家屋や敷地以外でも、相続や遺贈によって取得した被相続人の居住用家屋や敷地を売却したときには、譲渡所得から最高3,000万円控除できる特例があります。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といい、2024年12月現在、適用されるのは2016年4月1日~2027年12月31日までに売却した不動産です。
この特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
上記を満たした場合も、相続してから譲渡のときまで事業用に使用したり、貸し付けたりしていないことなど、特例の適用を受けるための要件が多く定められています。
参考:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
電子契約で印紙税がかからない
不動産売買では、これまで紙の契約書での契約が行われてきました。しかし、2022年5月に施行された宅地建物取引業法の改正により、電子契約ができるようになりました。印紙税は現状、紙の書面による「課税文書」を作成する際に必要となる税金であるため、電子契約の場合は、印紙税が発生しません。
不動産売買の取引金額によって印紙税額は異なり、税額は次の表のとおりです。
契約金額と印紙税額
| 記載された契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 10万円以下 | 200円 |
| 10万円超〜50万円以下 | 400円 |
| 50万円超〜100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円超〜500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 60,000円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超〜10億円以下 | 200,000円 |
例えば、不動産を3,000万円で売却した場合、印紙税は2万円です。
しかし、電子署名法にもとづく電子契約書は、税法上、印紙税の対象外とされているため、不動産売買の際に電子契約を活用することで、印紙税が不要になります。
不動産売却で税金がかからないときの注意点
不動産売却で税金がかからないと思われるときでも、自己判断では条件や要件を見落としてしまう可能性があります。つづいては、不動産を売却したときに税金がかからないときの注意点を解説します。
本当に税金がかからないか確かめる
別荘や投資用物件など居住用物件以外で出た赤字は損益通算できないため、税金が発生する可能性があります。損益通算とは、投資や事業で出た赤字(損失)を、別の投資や事業の黒字(利益)と相殺して、税金の支払いを減らせる仕組みのことです。
同じく不動産に関わる収入のなかで、マンションの賃料収入などの不動産収入がありますが、これは損益通算できます。しかし、不動産の譲渡所得は分離課税のため、一定の条件を満たす場合以外は給与所得や事業所得など他の所得と合算はできません。税理士など専門家に相談し、正しく把握し、申告することが大切です。
特例適用の条件や期限を確認してから申請する
不動産に関わる税金控除や特例にはさまざまなものがあり、適用条件や併用の可否、売却の期限などが細かく決められています。例えば、マイホームに関わる特例だけでも次のようなものがあります。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
- マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
それぞれ特例を適用できるマイホームの所有年数が決まっていたり、いつまでに売却しなければならないかが決まっていたりと、細かく定められています。
期限を過ぎたり、適用要件を誤ったりすると、3,000万円など大きな控除が使えなくなり納税額に数百万円の差が出ます。事前によく確認しておくことが大切です。
控除の適用により税金がかからない場合でも申告する
控除の結果税金がかからない場合でも、居住用財産の譲渡所得3,000万円の特別控除などの適用には、確定申告が必要です。控除が適用されて税金がかからないことを申告しなければなりません。
申告しない場合は控除が適用されないだけでなく、加算税や延滞税がかかる可能性があります。正確な手続きや申告内容については、税理士や税務の専門家に相談するのがおすすめです。専門家に確認することで、申告漏れや誤りのリスクを減らせるでしょう。
参考:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
不動産売却の節税ポイント
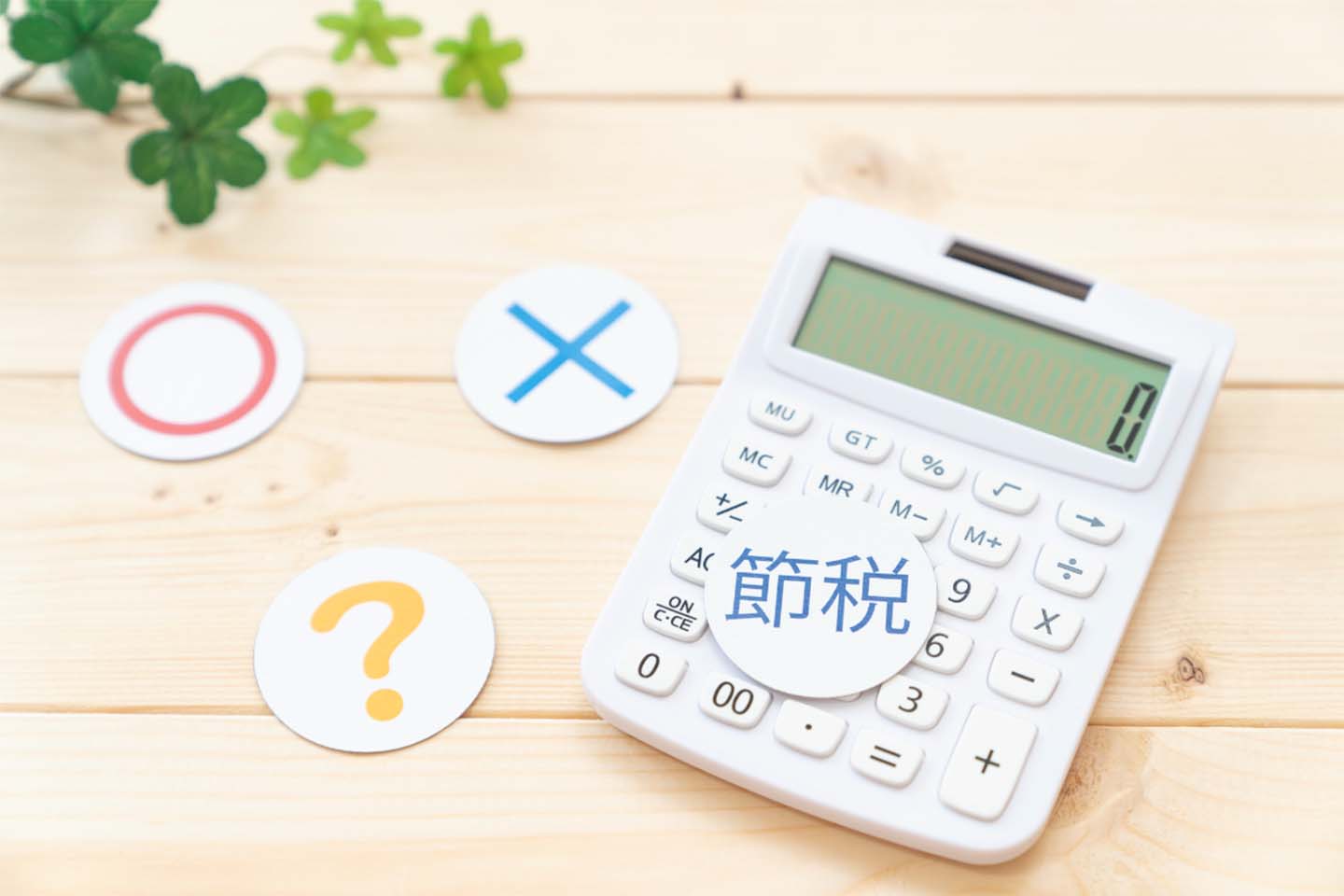
不動産を売却するときは取引価格が高額なため、1%税率が異なるだけでも納税額が大きく変わります。要件を正しく理解していないと、売却時期の少しのズレや、所有年数の少しの差で税率が変わり、数百万円の差になることもあります。ここでは、不動産売却の際に節税するポイントを確認していきましょう。
売却のタイミングを見極める
売却する不動産の所有年数や売却時期によって税金の取り扱いが異なるため、売却のタイミングを見極めましょう。例えば、所有年数が5年未満と5年超では、譲渡所得税の税率が次のように異なります。
所有期間別、譲渡所得税の税率
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 短期譲渡所得(5年未満) | 30% |
| 長期譲渡所得(5年超) | 15% |
課税譲渡所得金額が1,000万円の場合、短期譲渡所得と長期譲渡所得では税金に約150万円の差が出ます。このように、売却のタイミングによって納税額に差が出ることがあるので注意が必要です。
参考:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
利用可能な控除や特例を最大限活用
不動産の売却に使える控除や特例を最大限に活用することで、税負担を軽減できます。例えば、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を適用するかしないかで、納税額は大きく変わります。
3,000万円で購入したマイホームを、5,000万円で売却できた場合を考えてみましょう。譲渡費用を考慮しないものとすると、譲渡所得金額は2,000万円です。
特例を活用した場合は、譲渡所得の2,000万円から全額を控除でき、譲渡所得税がゼロです。
しかし、通常の長期譲渡所得税で計算した場合は、2,000万円×15%=300万円となり、納税額は約300万円です。特例は自身で申告する必要があるため、さまざまな特例について知っておく必要があります。
不動産会社に相談してみる
不動産に関する特例や控除は、自動的に適用されるものではありません。そのため、不動産会社や税理士に相談することで、自分では気づけない税金対策を提案してもらえる可能性があります。
また、個々の状況によって適用できる特例が異なるため、具体的な税務相談は専門家に直接ご相談ください。


