不動産売却のノウハウ

不動産を売却しても年末調整の対応は不要!
ただし確定申告が必要…?
不動産を売却すると、数百万円、人によっては数千万円もの収入を得ることになります。これだけ大きな収入があったら、年末調整が非常に面倒なことになりそうです。ところが、不動産を売却しても年末調整は必要ありません。しかし、人によっては確定申告が必要になるため、注意しましょう。年末調整と確定申告といった、不動産を売却したときの税金を解説します。
不動産売却 費用・税金2025年4月18日
目次
不動産を売却しても年末調整の対応は不要
結論から述べますと、不動産を売却しても年末調整の対応は必要ありません。年末調整とは会社員など給与で収入を得ている人が、源泉徴収で納め過ぎた税金を精算する制度のことです。年末調整の対象は給与所得のため、不動産売却でかかる税金は年末調整での対応が必要ありません。不動産を売却したときにかかる譲渡所得税は分離課税となり、給与所得などの所得とは分けて税額が算出され、それぞれ別に税金が課税されます。
なお、不動産売却時に利益が発生した場合は、確定申告が必要です。たとえば、不動産売却で1,000万円の利益を得た場合、原則としてその1,000万円が課税所得として課税対象となります。
不動産売却では確定申告が必要な場合がある
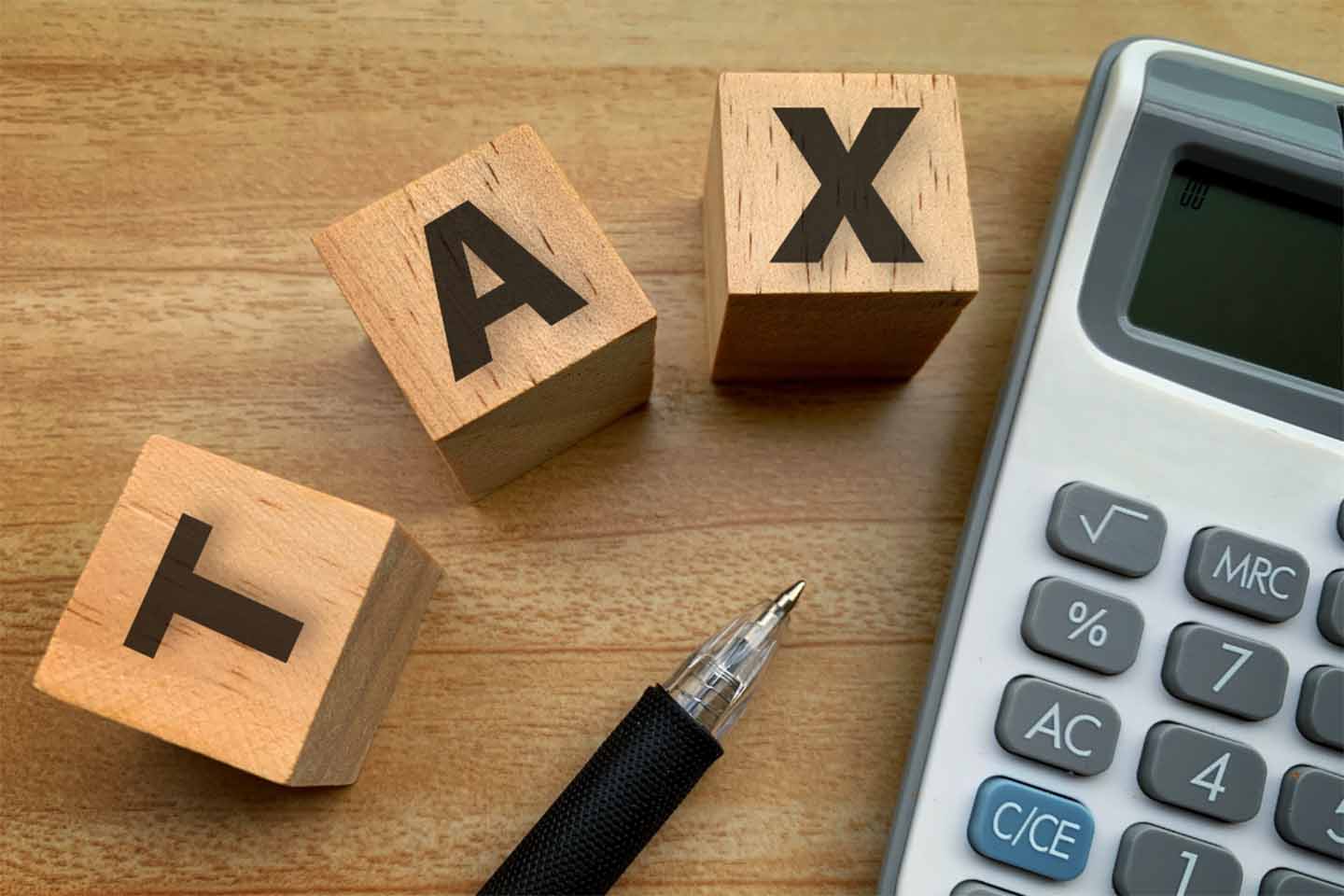
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、確定申告を行う必要があります。ここでは、確定申告の方法などをわかりやすく解説します。
確定申告とは
確定申告とは、所得税の計算をして税務署に申告する手続きのことです。所得税は、所得を得た人が自身で税額を計算し、申告・納付しなければなりません。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、青色申告の場合は10万円・55万円・65万円の青色申告特別控除があります。ただし、青色申告は事業所得(個人事業主など)や不動産所得(賃貸物件のオーナーなど)のある人が対象です。
なお、個人が不動産を売却した場合は、「譲渡所得」に該当するため、一般的な確定申告とは別の様式(譲渡所得の内訳書)で申告することになります。
譲渡所得を計算する方法
譲渡所得を計算する際の税率は、下図のように所有期間により異なります。
| 短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 | |
|---|---|---|
| 所有期間 | 5年以下 | 5年超 |
| 税率 | 39.63% 所得税:30.63% 住民税:9% |
20.315% 所得税:15.315% 住民税:5% |
不動産の譲渡の税金は、5年を超えているかどうかが分かれ目です。5年以上所有した物件は、税率が半分程度にまで低くなります。
不動産を売却したときの税金を計算する際は、最初に「譲渡所得」を算出します。計算式は以下のとおりです。
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)
譲渡収入金額(物件の売却金額)から、取得費(購入金額など取得時にかかった費用)や譲渡費用(売却時の諸費用)を差し引きます。取得費と譲渡費用には、それぞれ以下のような費用が該当します。
| 取得費 | 譲渡費用 |
|---|---|
|
● 購入代金、建築代金 ● 購入時の税金(印紙税、登録免許税、不動産取得税など) ● 仲介手数料 ● 測量費、整地費、建物解体費 ● 設備費、改良費 ● 一定の借入金の利子など |
● 仲介手数料 ● 印紙税 ● 借家人に支払った立退料 ● 建物解体費など |
取得費や譲渡費用の金額が大きいと差引金額も増えるため、譲渡所得税が少なくなります。
取得費がわからないときは
土地が先祖代々からのもの、あるいは親が購入した不動産など、取得費が不明なときは売却金額の5%を取得費として計算することが可能です。たとえば、不動産を2,000万円で売却した場合に取得費がわからないときは、売却金額の5%である100万円を取得費として利用できます。
実際の取得費が売却金額の5%以下である場合も、売却金額の5%を取得費として計上することが認められています。
ただし、5%の場合は差し引ける金額が少ないため、できるだけ売買契約書など取得費がわかる書類を見つけましょう。
確定申告を行う方法
不動産を売却して利益が出たときは、確定申告が必要です。確定申告は毎年1月1日から12月31日までの所得をまとめて所得税の計算をし、翌年2月16日から3月15日までに申告・納付を行います。
昔ながらの書類を作成する方法もありますが、近年ではマイナンバーカードを使ってインターネットからe-Taxソフトを利用して簡単に申告ができます。
e-Taxを利用する際は、利用者識別番号(半角16桁の番号)が必要なため、Webサイトからマイナンバーを使用してアカウントを作成しましょう。
e-Taxで確定申告を行うメリットは以下のとおりです。
- 税務署への持参が不要
- 印刷・郵送代が不要
- 添付書類提出不要(一部の書類を除く)
- 確定申告期間24時間利用可能
- 早期還付(3週間程度)
キャッシュレス納付で、現金をわざわざ下ろさなくても納税できます。
不動産売却で損失が出た場合も確定申告をおすすめする理由
売却益が出ないときは、確定申告を行う必要がありません。しかし、譲渡損失(マイナス)が発生した場合は以下の特例を利用すると、ほかの所得から控除(損益通算)できる場合があります。譲渡損失が発生したら、損益通算することで所得税や住民税が軽減されます。
| 特例 | 内容 |
|---|---|
| マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 |
● 売却後に一定の要件を満たすマイホームを買い換える ● 売却したマイホームの損失額が損益通算される |
| 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 |
● マイホームを買い換えなくても利用可能 ● 売却したマイホームの損失額、あるいは住宅ローン残高から売却額を引いた残額のいずれか小さいほうが損益通算される |
売却して損失が出たときは、これらの特例を利用しましょう。
特例を利用すると税金がかからないことも
不動産売却で確定申告をするときに、特例を利用すると税額が安くなります。ケースによっては税金がかからないこともあります。
マイホームの売却で利用できる主な特例をケース別にまとめた一覧表は以下のとおりです。なお、特例を利用するときは、譲渡所得税額が0円でも確定申告が必要です。
| 特例 | 内容 |
|---|---|
| 居住用財産の3,000万円の特別控除 |
● マイホームを売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる ● 居住期間を問わないが、前年や前々年にこの特例の適用を受けていると利用できない |
| 10年超所有軽減税率の特例 |
● マイホームを売却したとき所有期間が10年を超えていた場合、譲渡所得税率に軽減税率を適用できる ● 3,000万円の特別控除特例と併用可能 ● 譲渡所得が6,000万円以下の部分について譲渡所得税率を14.21%に抑えられる |
| 特定の居住用財産の買換え特例 | マイホームを売却した金額より買い換えたマイホームの購入金額のほうが大きいと、買い換えたマイホームを売却するときまで譲渡税を繰り延べできる |
ここからは、それぞれの特例について解説しましょう。
居住用財産の3,000万円の特別控除
マイホームを売却した場合、一定の要件を満たせば最高3,000万円の特別控除の特例を利用できます。所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円を差し引けるため、譲渡所得が3,000万円以下だと譲渡所得税がかかりません。ただし、確定申告をしないと3,000万円の特別控除を適用できないため、注意しましょう。3,000万円の特別控除は、10年超所有軽減税率の特例と併用できます。
10年超所有軽減税率の特例
10年以上所有したマイホームを売却した際、要件に該当すれば利用できるのが、10年超所有軽減税率の特例です。譲渡所得が6,000万円以下の部分について、譲渡所得税率を14.21%に抑えられます。
居住用財産の3,000万円の特別控除を利用しても、利益が出てしまう場合に利用できる特例です。売却金額によっては、数百万円もの譲渡所得税を節税できます。
特定の居住用財産の買換え特例
特定の居住用財産の買換え特例とは、10年以上所有するマイホームを売却し、一定の要件を備えた居住用の住宅に買換えた場合に利用できる特例です。買い換えた家を将来売却するまで、売却した自宅の譲渡益に対する課税を繰り延べられます。したがって、課税が免除されるわけではありません。
しかし、新居を購入する際には高額な資金が必要ですが、課税を将来に延ばすことで現在の資金負担を抑えられます。


