不動産売却のノウハウ
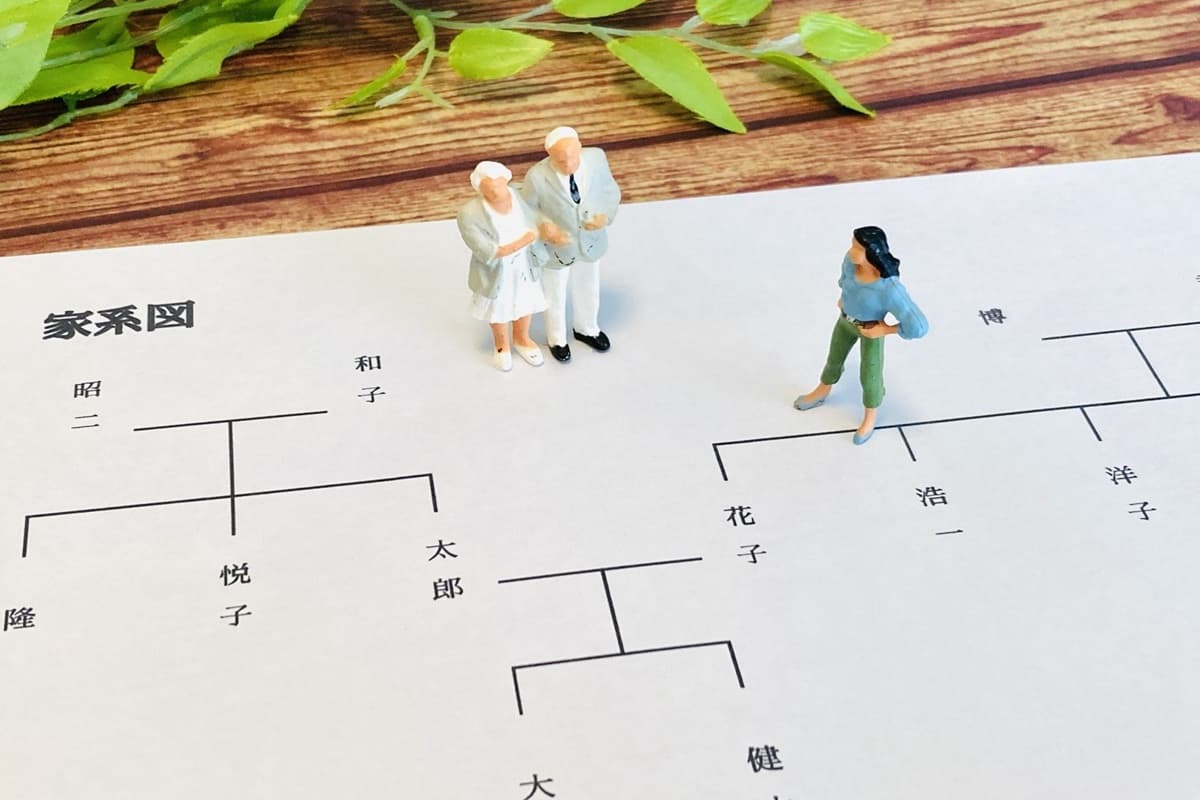
成年後見人が不動産売却する方法を知りたい!
トラブル事例や注意点も解説
成年後見人が不動産を売却する方法は通常の不動産売却と同じですが、家庭裁判所の許可が必要になるケースもあります。
成年後見人が不動産を売却する方法や注意点などを解説します。
不動産お役立ちコラム 不動産売却2025年7月22日
目次
成年後見人が不動産を売却する方法
成年後見人が被後見人の不動産を売却するためには、通常の不動産売却と変わりありません。
しかし、家庭裁判所による許可や成年後見監督人の同意が必要になるケースもあります。
成年後見の申し立てから進めていく場合は後見人の選任までに3〜4カ月、不動産売却の許可申請で1カ月がおおよそかかります。ほかにも不動産の売却活動が早くて半年から1年としても、トータルで1〜2年はかかるでしょう。
成年後見人とは
成年後見人とは、障害や認知症などにより被後見人の意向確認が困難な状態になった場合に、被後見人に代わり財産の管理や公的なサービスなどの手続きを行う人をさします。成年後見人制度を利用するためには家庭裁判所にて後見開始の審判とともに、成年後見人等の選任が行われます。
成年後見人等は家庭裁判所が最適と思われる人が選任され、親族のほか社会福祉士や司法書士、弁護士などの専門職、市民後見人、法人後見が対象です。成年後見人等は行なった事務について家庭裁判所へ報告するなどで、家庭裁判所または成年後見監督人等の監督を受けます。
「任意後見」と「法定後見」の2種類がある
成年後見人制度には、任意後見と法定後見があります。任意後見とは、障害や認知症などになるケースに備えて、被後見人が決めた人に代わりにやって欲しいことをあらかじめ決めておく制度です。
公正証書で任意後見契約を締結し、被後見人に心配事が現れたときに家庭裁判所での任意後見監督人の選任によって、任意後見契約の効力が生じることになります。
法定後見とは、被後見人に障害や認知症などで心配事が既に発生しているケースで、家庭裁判所によって成年後見人等が選定される制度です。
法定後見では、障害や認知症の程度によって、後見・保佐・補助いずれかの開始が審判されます。それぞれ代理で行える行為の範囲や同意・取り消しできる範囲が異なるため、被後見人の利益が最も尊重されるものを家庭裁判所で選定します。
選出は「後見人」「保佐人」「補助人」のいずれか
法定後見においては、後見人・保佐人・補助人のいずれかが選定されます。
後見人は被後見人が多くの手続きや契約を1人で決めるのが難しい方が対象となり、原則として全ての法律行為の契約・取り消し・代理を行うことが可能です。
保佐人は被後見人が重要な契約や手続きを1人で決めるのが難しい方が対象となり、借金や相続の承認のほか、申し立てによって裁判所が定める行為の契約・取り消し・代理を行うことが可能です。
補助人は被後見人が重要な契約や手続きの中で1人を決めるのが難しい方が対象となり、申し立てにより裁判所が定める行為について同意・取り消し・代理を行うことが可能です。
本人の障害や認知症などの程度に応じて、支援や補助が必要な範囲から後見・保佐・補助の開始の審判を受けることになります。
成年後見の申し立て方法と注意点
成年後見の申し立てを行うには、まず市区町村にある中核機関や地域包括支援センター、社会福祉協議会などの成年後見に関わりのある専門職のいる団体へ相談しましょう。成年後見制度の手続きや必要書類、成年後見人について相談にのってくれます。
その後、家庭裁判所に成年後見人制度の申し立てを行い、調査などを経て後見開始の審判と成年後見人が選任されます。成年後見の注意点として、1度開始されると被後見人が回復して1人で決められる状態になる、もしくは被後見人が亡くなるまで行わなければなりません。
また申立書には成年後見人の候補者の記入欄がありますが、家庭裁判所の判断により候補者以外の成年後見人が選任されることもあります。
そして、成年後見人はできることとできないことがあり、法律行為や預金管理等は行えますが、介護行為や日常生活の支援といった事実行為は行えません。
そのため、成年後見制度の利用を検討する際には注意が必要です。
成年後見人が不動産を売却する流れや注意点
成年後見人が不動産を売却する場合は、非居住用不動産の場合、通常の不動産売買と同様に不動産会社と媒介契約を締結し、売却活動を行います。買主が現れたら売買契約を結び、売却金額を受け取ったのち、不動産の引き渡しになります。
居住用不動産の場合は、売買契約後に家庭裁判所に申し立てを行い、許可を得てから売却金額を受け取る流れです。
家庭裁判所に申し立てする際には不動産の全部事項証明書や売買契約書などの必要書類があり、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
また、被後見人の生活費の補填など正当な理由なく売却することはできません。あくまでも被後見人のために必要な不動産売却でなければならないことに留意しましょう。
成年後見人が不動産売却 には許可や同意が必要

成年後見人が不動産売却するには家庭裁判所の許可や成年後見監督人の同意が必要になる場合があります。これらの許可や同意が必要なケースについて詳しく見ていきましょう。
居住用不動産の売却は家庭裁判所の許可が必要になる
成年後見人が居住用不動産の売却を行う場合は家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所に申し立てする際に成年後見監督人の同意が必要になります。許可を得るためには事前に成年後見監督人や家庭裁判所に話を通しておくと良いでしょう。
なお、任意後見の場合は原則として家庭裁判所の許可も成年後見監督人の同意も不要ですが、被後見人の生活費や医療費の補填など不動産の売買について正当な理由が必要です。
非居住用不動産は成年後見監督人の同意がいる場合がある
非居住用不動産の売却を行う場合は成年後見監督人がいるケースでは同意が必要ですが、いないケースでは原則として成年後見人の判断で売買できます。ただし、正当な理由なく売買が行われた場合は後で問題視される可能性があるため、留意しておきましょう。
居住用か非居住用か判断する方法
成年後見人の不動産の売却において、対象不動産が被後見人の居住用か非居住用かどうかを判断するには本人の生活実態が判断材料となります。現に居住しているだけでなく、過去に生活の拠点となっていたりしても居住用不動産に該当するケースもあります。
許可されるかどうかの判断基準
成年後見人が不動産売却するために家庭裁判所から許可されるかどうかの判断基準としては、下記の5点から判断されます。
- 本人の財産状況と照らし、本当に必要な処分かどうか
- 介護施設への入所や病院への入院、帰宅の見込み、または本人の考えはどうか。特に帰宅の見込みがある場合は、帰宅先をどのように確保するのか
- 売却条件が適当な内容か
- 売却代金が被後見人のために使われるようになっているか
- 推定相続人である親族が対象不動産の処分に反対していないかどうか
不動産を売却する理由が適切かどうかは、弁護士や弁護士と提携する不動産会社へ相談してみると良いでしょう。
事例から学ぶ、成年後見人の不動産売却トラブルを防ぐコツ
成年後見人における不動産売却トラブルを未然に防ぐためには、どのような事例があるのかを知っておくことが重要です。ここでは、具体的な例をもとにトラブルを防ぐコツについてみていきましょう。
認知症の親が勝手に不動産を売却した事例
認知症の親が所有していた不動産を勝手に売却した事例についてみていきましょう。当時認知症を患っていた親が親族に相談せずに不動産を売ってしまい、相場よりも低額で売却してしまったケースです。
民法では認知症など意思確認ができない場合に、契約自体が無効とされています。成年後見制度を活用すれば、被後見人が行なった法律行為を取り消しできます。
軽度の認知症で貸金業者からの借金を繰り返していた事例
軽度の認知症で貸金業者からの借金を繰り返していた事例についてみていきましょう。家事がままならなくなり、貸金業者から繰り返し借入するようになっていました。子供が成年後見制度の補助人に選任され、本人が子供に相談せずに行なった借入について取り消しできるようになりました。


