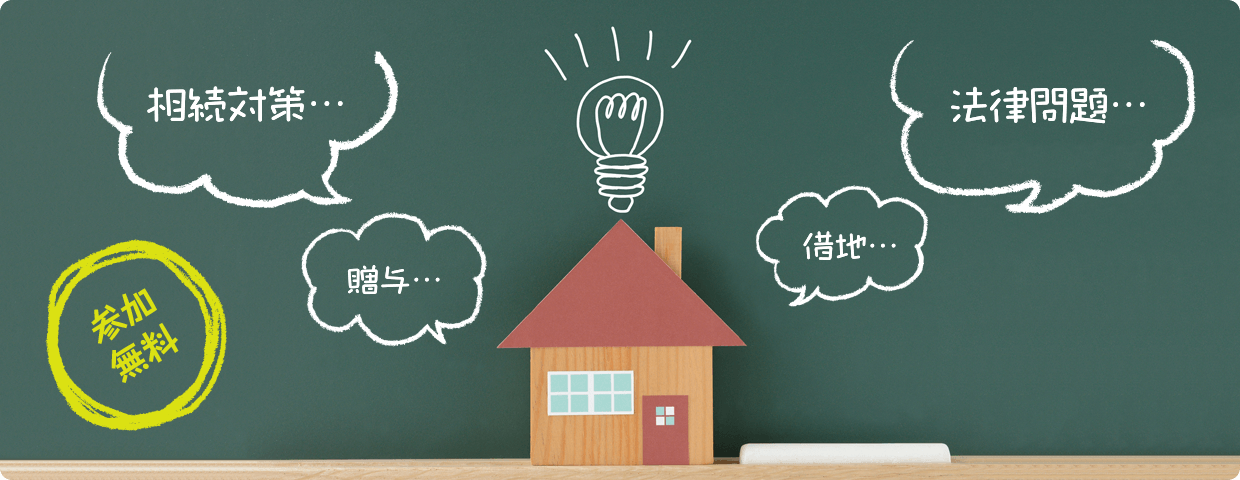不動産売却のノウハウ
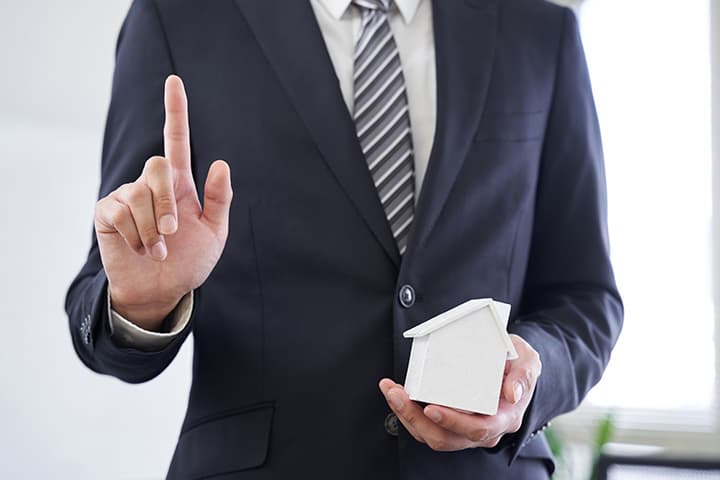
相続した不動産の売却に関する注意点!税金や確定申告はどうする?
相続した不動産の売却を検討しているものの、ほかの相続人との分割や確定申告など、各種手続きの方法が分からず困る方もいるでしょう。
特に共有名義で不動産を相続した際には、共有者の同意を得る必要があるため、慎重な対応が求められます。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際に知っておきたい注意点を、売却前・売却活動中・売却後の3工程に分けて詳しく解説します。後半では、不動産を売却した際に利用できるお得な特例も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
2022年5月20日
目次
売却前の注意点
まずは、売却前に注意する点を紹介します。
相続不動産の名義について
不動産を相続する人が決まれば、相続人全員で遺産分割協議書を作成します。それを証拠書類として、法務局で不動産の名義変更を行います。
この不動産の名義で注意するのは、「なるべく共有名義で相続しない」ということです。
現金や預貯金と異なり、不動産は公平に分けるということが難しい遺産です。だからといって安易に共有名義にしてしまうと、その後、処分に苦労します。
共有名義の不動産を売却などで処分する場合には、共有者全員の同意が必要です。1世代、2世代と相続が進むごとに共有者は増えていくため、「気がつけば会ったこともない親戚と売却について相談しなければならない」ということが発生してしまいます。
そのため、不動産はなるべく単独で相続することが望ましいでしょう。
相続不動産の分割について
不動産が遺産の中で多くの割合を占めており、単独相続すると不公平になってしまう場合はどうすればよいのでしょうか。
不動産の分割方法には、以下の3つがあります。
- 代償分割
- 換価分割
- 現物分割
この中でも、代償分割もしくは換価分割の方法を選択することで、公平に遺産分割ができます。
代償分割
代償分割とは、相続人のひとりが財産を単独相続する代わりに、ほかの相続人に対して差額を支払う方法です。
たとえば、相続人2人が不動産5,000万円、預貯金3,000万円の計8,000万円を相続するとしましょう。この場合、不動産を相続した側が、預貯金を相続した側に1,000万円を支払えば、2人の額は4,000万円ずつと公平にできます。
代償に用いる財産は相続人固有の財産でもよいです。そのため、不動産を相続した相続人が自らの預貯金から1,000万円を支払うことも可能です。
換価分割
換価分割とは、財産を売却し、その代金を相続人全員で分配する方法です。
たとえば、相続人2人が5,000万円の価値がある不動産を相続する場合では、不動産を売却した後2,500万円ずつ分け合うことができます。
不動産の売却には時間を要することが多いため、換価分割を行う場合は、いったん共同相続人全員の名義にするのが一般的です。
代表者名義にすることも可能ですが、この場合は遺産分割協議書に「換価分割のために便宜上、名義変更する」ことを書き残しておく必要があります。
共有で所有する場合
共有名義で不動産を売却する際は、代表者が共有者全員から、売却の同意を得ることが重要です。
売却に同意しない人がいる場合は、共有で持ち続けることのデメリットと売却により得られる資金配分を説明し、納得してもらいましょう。
その中で、売り出し価格を相談します。売却を依頼する不動産仲介会社に価格査定してもらい、その結果を共有者に伝えましょう。査定では周辺相場などの参考情報も知ることができるため、可能であれば一緒に不動産仲介会社の説明を聞いてもよいでしょう。
できれば、事前に「いくら以上であれば売却する」という合意形成を取っておくと、スムーズに売却を進められます。
なお、共有名義の不動産を売却する場合、共有者全員の同意や立ち合いが必要です。全員がそろわない場合は、委任状を受け取っておくことで代表者が手続きをすることが可能です。
必要な書類を準備しておく
売却前に、必要書類を準備しておきましょう。
一般的に必要となる書類は以下のとおりです。
| 書類 | 説明 |
|---|---|
| 土地・建物の登記済証 (権利証) または登記識別情報 |
所持者が不動産の持ち主(登記名義人)であることを証明する。 |
| 各種図面 | 測量図や建物図面など、その不動産を取得した際に受け取った図面。 |
| 本人確認書類・ 実印・印鑑証明書 (3カ月以内に発行したもの) |
共有の場合、全員分が必要。 |
| 固定資産税・ 都市計画税納税通知書 |
毎年、地方自治体から所有者に送付される書類。不動産の買主と税負担の割合を清算するために必要。 |
| 建築確認通知書・ 検査済証 |
建物の場合、建築基準法に定められた内容に合致していることを証明する。 |
実際には、不動産仲介会社から指示があるため、その指示に従いそろえましょう。
売却活動中の注意点
必要書類の準備や、ほかの相続人との話し合いなどが終われば、次は実際に不動産の売却活動を始めます。
売却活動中に注意する点を確認しておきましょう。
内覧対応
一般的には、鍵を不動産仲介会社に預ければ、後は不動産仲介会社が募集や内覧の対応をしてくれます。
しかし、物件の魅力が少しでも伝わるよう、売主も内覧の準備はしっかり行っておきましょう。
建物内に家具や不用品があると、床や天井を見ることができません。あらかじめ、すべて撤去しましょう。
撤去した後に、ハウスクリーニングを行います。その際、押し入れや浴室などに湿気によるカビが生えている場合は、きちんと除去しておきましょう。
売り出し価格の変更
売却が始まった後は、定期的に不動産仲介会社の報告を受けましょう。
- 内覧の件数
- 内覧に来た人はどのようなことを望んでいるのか
上記などを把握しましょう。
なかなか思うように売却が進まない場合は、不動産仲介会社と相談して、売却価格を下げるなどの対応が必要です。
不動産が共有名義の場合は、ほかの共有者にも同意を得ておいたほうがよいでしょう。「もっと高い値段で売ってほしい」という要望がある人がいるかもしれません。
客観的な事実を説明しつつ、合意形成を図りましょう。
売買契約締結・引き渡し
無事に購入者が決まった後は、売買契約の締結と引き渡しを行います。
契約書には、共有者全員の署名捺印が必要です。共有者全員が一堂に会することが難しい場合は、代表者1名を代理人に設定し、委任状を作成するとよいでしょう。
売却金額の振込みを確認した後に、登記済証(権利証)または登記識別情報を引き渡せば、無事取引は完了です。
売却後の注意点、税金や確定申告

売却が完了した後は、譲渡所得に関する確定申告を行わなければなりません。
もし共有名義の場合は、共有人それぞれが、持ち分に応じて自らが得た譲渡益に対する確定申告を行います。
税金の支払い
不動産を売却する場合、以下の税金が発生します。
| 内容 | 税率 | ||
|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 不動産の名義変更登記にかかる税金 | 不動産の価額の0.4% | |
| 印紙税 | 売買契約書の作成にかかる税金 | 2,000〜10万円売買契約書の金額により異なる | |
| 譲渡益に対する 所得税・住民税・復興特別 |
不動産の売却益に対してかかる税金 | 所有期間5年以下 | 譲渡所得の39.63% |
| 所得税 | 所有期間5年超 | 譲渡所得の20.315% | |
原則、税金含めたこれらの費用は、共有名義人全員がその割合に応じて支払う必要があります。
譲渡益に対する所得税
税金の中でも、もっとも税額が高くなるのが、住民税と復興特別所得税を含む、譲渡益に対する所得税です。
譲渡所得税は譲渡で出た利益に対してかかります。利益を計算するためには、売却金額から取得時や売却時にかかった費用を差し引く必要があります。
計算式は以下のとおりです。
譲渡所得=売却金額-(取得費+譲渡費用)
なお、売却完了後、譲渡所得税を計算するために、購入時の契約書など、金額が分かる資料を用意しておくとよいでしょう。
利用できる特例
相続した不動産を売却した際には、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が利用できるケースがあります。
これは、支払った相続税の一定額を取得費として計上できるというものです。相続で取得した不動産を、相続発生日から3年10カ月以内に売却した場合に適用できます。
たとえば、相続税300万円を支払い相続した不動産を5,000万円で売却できたとしましょう。取得時にかかった費用(本体価格含む)が3,000万円、売却時にかかった費用が200万円の場合、利益1,800万円に対して所得税がかかります。
特例を利用すると、相続時に支払った税額である300万円分、利益を圧縮できます。
不動産譲渡にかかる所得税の税率は、所有期間5年以内である短期譲渡の場合で39.63%、所有期間5年超である長期譲渡の場合で20.315%です。
短期譲渡の場合だとしても、300万円所得を圧縮することで、300万円の39.63%である約119万円の節税効果を見込めます。
相続不動産に詳しい不動産会社に相談しよう
今回は、相続した不動産を売却する場合の注意点について説明しました。しかし、相続不動産は複雑な手続きなどが多く、自分だけで行うのは難しいのが実情です。
税金に関しては税理士に依頼することで、委託報酬以上に節税効果が出る場合もあります。
また、相続不動産の取扱い実績が豊富な不動産会社に依頼すれば、安心して任せられます。不動産を相続した人だけでなく、相続予定の方も早い段階から相談して計画しておくことが大切です。