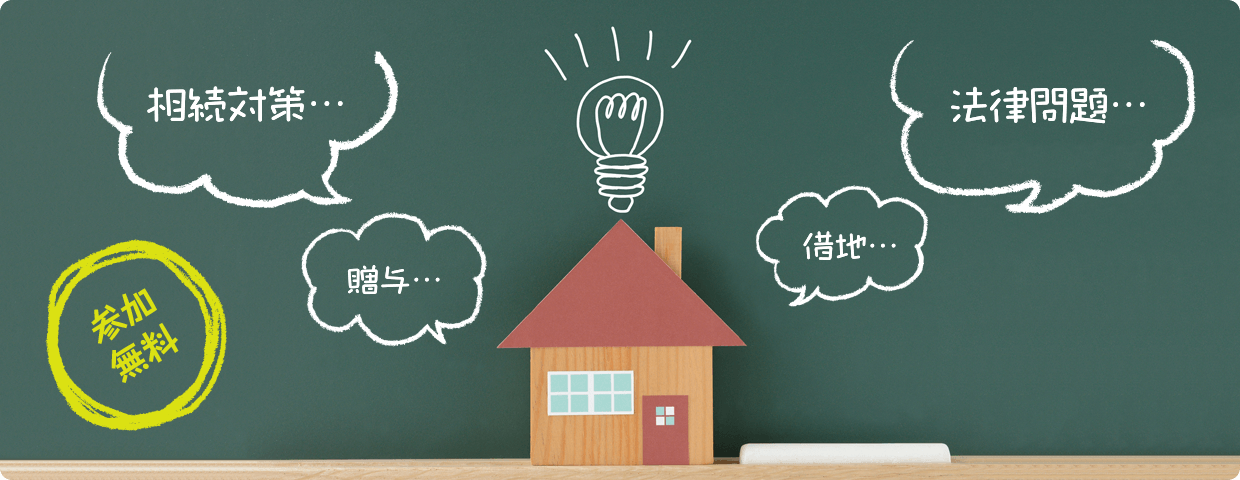不動産売却のノウハウ

相続した不動産の売却時に取得費に含まれるもの。
取得費不明の場合はどうする?
税金を把握するために不動産譲渡所得を計算する時、特に分かりづらいとされるのが取得費です。
取得費とは売却する不動産を購入した時の費用ですが、相続した不動産の場合は取得費をどう考えるのでしょうか。
- 取得とはいつのことか
- どのような支払いが取得費となるのか
- 取得費が不明の場合はどうするのか
本記事では、相続した不動産を売却する際の取得費の考え方や、実際に含まれるものを詳しく解説します。また、特例を利用することで節税できることもあるため、併せて確認しておきましょう。
2022年5月20日
目次
相続した不動産における取得費
取得費の基本的な考え方を確認しておきましょう。
取得費とは
不動産の売却など譲渡による譲渡所得は以下の計算式で求められます。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費-特別控除額
譲渡所得には、税金が課せられます。本来取得費にできる金額を含めずに計算した場合、所得が増えてしまい、余分な税金を支払うことになります。
そのため、取得費に入る費用は正確に把握しておくことが重要です。
不動産を購入した代金のうち、土地分は取得費になります。
建物の場合は、購入代金や建築代金の合計金額から、減価償却費相当額を差し引いた金額を取得費とします。
またほかにも、購入した時の登記費用や登記免許税、測量代などが取得費に該当します。詳しくは後ほど紹介します。
建物の取得費
建物の購入代金はそのまま取得費にはなりません。購入代金から減価償却費相当額を差し引いた金額を取得費とします。
建物は土地と違い、経年劣化などで価値が下がっていくという減価償却の考え方があります。そのため、建物の耐用年数に応じて分割して毎年計上する方法が採用されています。
減価償却費は建物の用途や構造によって異なります。
住宅は非事業用の建物として、次のような計算式で求められます。
減価償却費=建物購入費 × 0.9 × 法定耐用年数の1.5倍に応じた償却率 × 経過年数
法定耐用年数の1.5倍に応じた償却率は、国税庁の「主な非業務用資産の償却率」で確認しましょう。
たとえば2,000万円で購入した木造住宅が、20年経過したとすると次の式になります。
減価償却費=2,000万円 × 0.9 × 0.031 × 20年=1,116万円
つまり、取得費は次のとおりです。
取得費=2,000万円-1,116万円=884万円
不動産の所有期間は?
不動産の譲渡所得計算では、長期譲渡か短期譲渡かによって、税率が異なります。
相続した不動産の場合、被相続人が取得した日から計算します。相続してからの期間ではないことに注意しましょう。
長期譲渡と短期譲渡のそれぞれの税率は以下のとおりです。
| 長期譲渡 | 短期譲渡 | |
|---|---|---|
| 所得税(%) | 15 | 30 |
| 住民税(%) | 5 | 9 |
| 復興特別所得税※(%) | 0.315 | 0.63 |
| 合計(%) | 20.315 | 39.63 |
※復興特別所得税…東日本大震災からの復興のために設けられた、2037年12月31日まで徴収される特別な措置
取得費に含めることができるもの

下記の表は、相続不動産を売却した時の取得費の一覧です。被相続人と相続人が支払った費用でそれぞれ該当するかを確認してみましょう。
| 被相続人が支払った費用 | 相続人が支払った費用 | |
|---|---|---|
| 土地購入代金 | 〇 | - |
| 建物購入代金または建築代金-減価 | 〇 | - |
| 償却相当額 | ||
| 所有権移転登記費用 | 〇 | 〇 |
| 不動産取得税 | 〇 | 相続は不動産取得税が課税されない |
| 印紙税 | 〇 | これらの費用は譲渡費になる |
| 土地の造成費用 | 〇 | |
| 土地の測量代 | 〇 | |
| 賃借人の立ち退き費用 | 〇 | |
| 訴訟費用 | 〇 | |
| 取得後1年以内の解体費用と建物分の購入代金 | 〇 | |
| 契約解除違約金 | 〇 |
被相続人が支払った費用は取得費になり、相続人が支払った費用のほとんどは譲渡費になります。
土地代や建物代
土地と建物の取得費はそれぞれ前述のとおりですが、建物については、相続してから償却する部分があります。そのため、相続から売却までの期間が長いほど取得費は少なくなります。
土地と建物を被相続人が取得した費用は、以下のもので確認できます。
- 売買契約書
- 請負工事契約書
- 領収書
取登記費用や税金
被相続人が取得時に支払った登記費用と、相続人が支払った登記費用は取得費に入れます。なお、登記費用には登録免許税を含みます。
被相続人は不動産取得税も支払っているので、これも取得費になります。
いくら支払ったのかは、それぞれ以下を確認します。
被相続人が支払ったこれらの領収書は、登記済権利証もしくは登記識別情報通知書といっしょに保管していることが多いです。
税金関係の領収書や納税証明書も、登記済権利証といっしょに保管されていることが多いでしょう。
土地の造成費用と測量代
被相続人が取得時に土地を整地するなど、利用目的に合わせて土地の形質を変更した工事代金は取得費に含まれます。
さらに土地の境界が判然としないまま取得し、隣接する土地所有者とのトラブルを防止するために行った測量代なども同様です。
工事代金や測量代金として被相続人が支払っていた費用の領収書は、登記済権利証といっしょに保管していることも多いです。そのため、丹念に書類が保管されているところを確認しましょう。
立ち退き費用や訴訟費用
不動産を取得する時点で賃借人がおり、賃貸借契約の解約と立ち退きをしてもらうために支払った立ち退き料は取得費になります。
さらに被相続人が取得する際に、所有権の完全な行使を阻害するおそれのある紛争があったケースがあります。その紛争を解決するために行った訴訟費用が取得費となります。しかし、遺産分割協議に関わる訴訟は該当しないので注意しましょう。
これを確認するためには、賃借人の領収書や弁護士事務所の領収書などを探しだす必要があります。
取壊し費用と建物分購入費
古家付きの土地を取得しておおむね1年以内に建物を取壊して処分した場合、取壊し費用は取得費として算入できます。
また、被相続人が取得した時点の売買価額に建物分の価額が含まれている場合、その価額も取得費にできます。
そのためには、取壊し工事の契約書や領収書および売買契約書が必要です。
おおむね1年以内という規定は、国税庁の「所得税法基本通達」38-1で定めているものです。ここでは、以下のように明記されています。
取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初からその建物等を取壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、(以下省略)
1年を経過した場合や取壊しの目的が通達と異なる場合は税務署に相談することをおすすめします。
契約解除違約金
被相続人が不動産を取得した時、同時期に別の物件を買うことを予定していることがあります。相続によって、その購入が必要なくなり、締結していた売買契約を解除するケースがあります。
この場合に、契約書にしたがって支払った違約金は取得費に算入できます。
当時の相手方が発行した領収書が必要ですが、対象不動産の売買契約関係書類の中にあるかもしれませんので、よく探すようにしましょう。
【補足】取得費不明の場合
取得費を証明する書類を、被相続人がきちんと保管している場合は確認をしやすいでしょう。しかし、時間が経過していると、紛失して所在が不明な場合があります。
このような時は取得費を譲渡価額の5%とすると、法令で決まっています。
たとえば相続した土地を2,000万円で売却した場合は、100万円が取得費になります。ただしこの場合は相続人が支払った相続登記費用などは、取得費にならないので注意が必要です。
詳しくは、国税庁「No.3258 取得費が分からないとき」を確認してみましょう。
相続した不動産をお得に売却するポイント
不動産を売却すると、譲渡所得に対して税金が課されます。
取得費についてここまで解説してきましたが、相続不動産に特有の特例制度を利用してお得に売却できます。
取得費加算の特例を利用する
相続財産を譲渡した場合には、課税された相続税を取得費に加算できる特例があります。
特例の適用を受けるには次の要件を満たす必要があります。
- 適用されるのは相続または遺贈により財産を取得した人
- 取得した人は相続税を課税されている
- 相続開始した日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年経過の期間内に譲渡した場合
すべての要件を満たすと、課税された相続税の一定額を取得費として加算できます。
また、相続税申告期限は10カ月ですので、相続してから3年10カ月以内の譲渡に適用できます。
計算は次の手順で行います。
- 譲渡した不動産の相続税課税価格と相続財産すべての相続税課税価格(債務控除前の課税価格)の割合を求める
- 手順1で求めた割合を相続税額に乗じる
具体例として、以下の条件で考えてみましょう。
土地:5,000万円
預金:3,000万円
借金:2,000万円
相続税:1,700万円(基礎控除は無視しています)
この場合で取得費に加算できる金額は、手順に沿って次のとおり計算できます。
- 5,000万円 ÷ 10,000万円=0.5
- 1,700万円 × 0.5=850万円=取得費加算額
計算した結果が取得費に加算できる相続税額になります。
ただし特例加算をしないで計算した譲渡益よりも、加算できる相続税額が大きい場合があります。そうすると、譲渡益相当額が加算できる相続税額となり、結果は譲渡益がゼロになります。
相続財産の売却は特例の期限に注意
相続財産を売却する時には、取得費加算の特例のように、期限が過ぎてしまうと適用できないものがあります。
相続した空き家や敷地を売却した場合の3,000万円控除がそのひとつです。譲渡所得から3,000万円控除できる制度ですが、2023年12月31日までに売却することが条件です。
さらに以下の適用要件があります。
- 空き家は被相続人が居住していた住宅と敷地
- 相続開始から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売却
- 売却代金は1億円以下
- 売却相手は近親者ではない第三者
- 住宅は1981年5月31日以前の旧耐震基準でありながら、譲渡時に一定の耐震基準を満たしている
- 住宅や敷地を相続から譲渡までの期間、事業や貸付の用途として使用していない
ここで適用の難しいのが、譲渡時に一定の耐震基準を満たしていることですが、この基準を満たせない場合は住宅を取壊して土地として売却しても適用されます。
実績がある不動産会社に相談する
相続した不動産の売却では思わぬアクシデントが発生し、スムーズに売却できない場合もあります。
たとえば相続不動産といっても、実は相続登記がまだなされていないケースがあります。単に登記手続きを進めていなかったという理由であれば、大きな問題になることはありません。
しかし、以下のような事情で、相続登記以前の問題が解決していないケースがあります。
- 遺産分割協議が中断している
- 相続人の中に連絡の取れない人がいる
また、相続登記は終わっていても共有者から同意が得られない、あるいは共有者と連絡が取れないなどにより、売却活動ができないケースもあります。
相続不動産の売却では、初期の段階から経験豊かな不動産会社と相談しながら進めることが大切です。