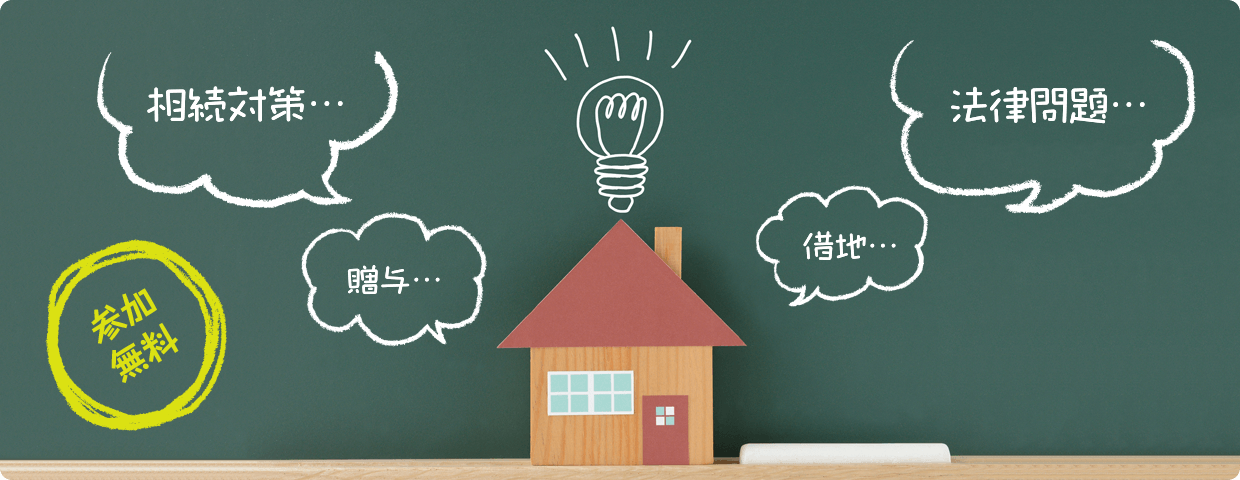不動産売却のノウハウ

土地の賃貸借契約の期間について解説。
契約時の注意点とは
賃貸借契約とは、基本的には賃借人を守るよう設定されています。貸主の勝手な事情で借主の生活を脅かすことがあってはならないためです。
土地の賃貸借契約では建物を建てる目的があるか、そうでないかによって、借地借家法か民法が適応されるかが分かれます。それぞれで契約期間は異なります。
そして土地の借地期間は数年ではなく、何十年と設定されることが多いので、契約期間中のトラブルも多くなります。
今回は、土地の賃貸借契約の契約期間と、それにまつわるトラブル事例について紹介します。
2022年1月6日
目次
土地を賃貸借する際の契約期間
平成4年(1992年)8月1日、「借地借家法」が施行され、平成4年(1992年)7月31日までの土地の賃貸借に関しての法律「借地法」(以降「旧借地法」)から変更となりました。
しかし、平成4年(1992年)8月1日以前に賃貸借契約を交わされているものに関しては従前の「旧借地法」が該当します。これらはいずれも土地に建物が存在していることが条件の法律で、建物がない場合においては「民法」が適用されます。
それでは、それぞれの契約期間について説明します。
借地借家法が適用される場合
平成4年(1992年)8月1日、借地借家法が施行された以降に賃貸借契約を行った場合に適用されます。
土地の賃貸借(借地契約)における契約期間について
借地借家法3条において、契約時に期間を定めなかった場合、定めた場合によって期間が変わります。
| 契約時 | 期間 |
|---|---|
| 期間を定めなかった場合 | 30年 |
| 期間を定める場合 | 最低30年 |
また、当事者間で上記に示した長い期間を定めることはできますが、短い期間は定められません。
契約更新後の存続期間
契約更新回数においては借地借家法4条において期間が決められています。
| 更新回数 | 期間 |
|---|---|
| 1回目 | 最低20年 |
| 2回目以降 | 最低10年 |
また、当事者間で上記に示した長い期間を定めることはでき、上限はありません。
旧借地法が適用される場合
平成4年(1992年)8月1日に施行された借地借家法以前に結ばれた土地の賃貸借契約(借地契約)の期間につきましては借地借家法ではなく、「旧借地法」が適用されます。契約が更新されても借地借家法でなく「旧借地法」が適用されます。
土地の賃貸借(借地契約)における契約期間について
借地上の構造物の種類に応じて借地法2条1項により契約期間が決まっています。
・契約期間を定めなかった場合
| 借地上の構造物 | 期間 |
|---|---|
| 堅固建物(けんごたてもの) (鉄骨造りや石造りなどの頑丈な建物等) |
60年 |
| 非堅固建物 (木造などの頑丈ではない建物) |
30年 |
・契約期間を定める場合
借地上の構造物の種類に応じて借地法3条において契約期間が決まっています。
| 借地上の構造物 | 最低契約期間 |
|---|---|
| 堅固建物 | 30年 |
| 非堅固建物 | 20年 |
・契約で「堅固建物」を建てることが目的であると明示されていない場合、「非堅固建物」を建てる目的であったものとみなされます。
契約更新後の存続期間
契約更新後についても借地法により契約期間が決められています。
「堅固建物」は最低30年、「非堅固建物」については最低20年(借地法5条1項)としなければならず、これより長い期間を当事者間で定めることは可能です(借地法5条2項)。その場合の上限はありません。
| 借地上の構造物 | 最低契約期間 |
|---|---|
| 堅固建物 | 30年 |
| 非堅固建物 | 20年 |
民法が適用される場合
建物所有以外の目的の土地の賃貸借契約には、借地借家法の適用はありません(借地借家法2条1号参照)。
たとえば、資材置き場や駐車場などで土地を貸し出す場合などがこれにあたります。
つまり、建物がない場合、民法が適用されます。
契約期間については、民法の定めるもとで決めることになりますが、民法においては、賃貸借の契約期間は50年を上限としています(民法604条1項前段)。これより長い期間を決めた場合においても契約期間は50年となります(民法604条1項後段)。
加えて、定めが下限についてはないので、50年以内の期間で、自由に決めることができます。契約期間を1カ月とする短期の契約も交わすことができます。
土地の賃貸借においての契約終了時の注意点

契約をした日により、また建物の有無により適用する法律と契約期間について説明しました。
では、契約終了時においてどのような点が異なるのかについて解説します。
借地借家法が適用される場合
借地借家法上において、土地の賃借人が賃貸人に対し、賃貸借契約の更新を請求した場合や、賃貸借期間満了後、賃借人が土地の使用を継続している場合には、賃貸人が遅滞なく異議を述べないかぎり(更新拒絶の意思表示)、賃貸借契約は更新されます(借地借家法5条1項、2項)。
また、賃貸人が意義を申し立てるには正当の事由があると認められる場合でなければなりません。(同法6条)。
正当事由については下記の事例より判断されます。
- 借地権設定者(賃貸人)及び借地権者(賃借人)が土地の使用を必要とする事情
(具体例:賃貸者が建物を建てて住居として使用する、ビル等を建て自分の事業として使用する など) - 借地に関する従前の経過
(具体例:権利金、更新料が支払われたかどうか、賃料の滞納の有無、用法義務違反の有無、賃貸人への嫌がらせがなかったか、など) - 土地の利用状況
(具体例:土地上に建物があるか否か、その種類や用途、構造・規模、建物の築年数や老朽化の度合い、借地権者の利用状況等) - 借地権設定者が土地の明け渡し後の条件としてまたは土地の明け渡しと引換えに借地権に対し財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出
(具体例:立退料がこれにあたります)
旧借地法が適用される場合
借地借家法6条の規定は、旧借地法が適用される賃貸借契約には適用されないものではありますが、これまでの判例で採用されてきた正当事由の判断基準を明文化したものであり、旧借地法が適用される場合においても、借地借家法6条と同じように考えることができます。
民法が適用される場合
貸主及び借主の間で賃貸借の期間を定めなかった場合においては、いつでも解約の申入れをすることが可能で、その場合、土地の賃貸借は、解約の申入れの日から1年間を経過することによって終了する、と示されています。(民法617条)。
契約時の確認不足によるトラブル例
賃貸借契約においての解約期間や契約終了時における更新について解説しました。
契約時にうっかり確認を忘れるとトラブルに巻き込まれることも少なくありません。
では、どのようなトラブルなのでしょうか。
中には契約書にうたわれていない事項もありますので十分注意する必要があります。
承諾料・更新料の有無
承諾料とは、賃借人が賃貸人に対して認めてもらう諸条件(借地の条件変更、増改築の許可、借地権の譲渡など)の代わりに支払うお金のことをいいます。更地価格の3~10%を要する場合があるといわれております。
更新料とは、文字通り契約更新時に必要な費用のことで判例においては一般的に更新料の支払義務を認めていませんが、実際には全国的に更新料の請求が行われているのが実態です。
契約の時点で十分に話し合い、更新料を設定している理由、金額を理解し、お互いが納得の上で契約を結ぶことが大切です。
地代の値上げ
賃料の地代の変更が認められるのは、あくまで正当な理由がある場合に限られます。
例えば、
- 税金等、土地にかかる経費の増加があった場合
- 経済事情の変動により物件の価値に変動があった場合
- 近隣の同種物件と賃料の大きな乖離がある場合
があります。
賃料の値上げに納得できない場合、借主は相当と認める賃料を供託することができます。
賃料を支払わない場合、債務不履行で賃貸借契約を解除されたり、損害賠償を請求される恐れもありますが、賃料を供託することで、最悪の事態を免れることも可能です。
諸条件を契約時に確認し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。